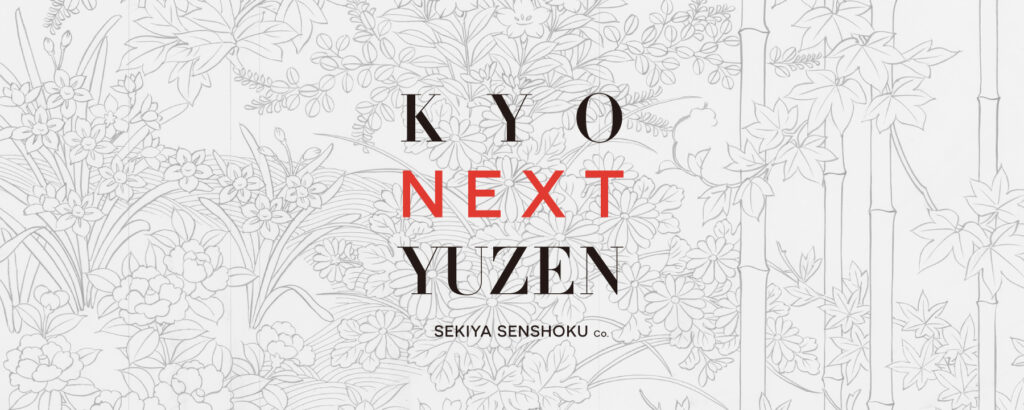Magazine

「ものづくりとコンテンツの融合」をめざすICOMAが考えるNFTの可能性
- Feature
- Interview
HINATAオープニングキャンペーンに協力いただいた「タタメルバイク」を企画・開発する株式会社ICOMA 代表取締役の生駒崇光さんに特別インタビューを実施!気鋭のハードウェアスタートアップ代表の生駒さんが考えるNFTの可能性などについてお伺いしました。

「ものづくりとコンテンツの融合」を目指す
ーー今回、HINATAを通してタタメルバイクのアートをNFT化することにチャレンジされた背景をお聞かせください。
生駒)まず大前提として、我々は「タタメルバイク」の実車を世に送り出せるよう、開発に全精力を注いでいます。今年早々には新しい試作機も発表できる予定です。
なので今回HINATAさんに知人経由で運良くお声がけいただきましたが、デジタルアートとして大きく話題化できるような新作アートの制作リソースは現状なく、ゆえに今回のNFTキャンペーンの目的もお金やマーケティングではありません。
我々の「ものづくりの思想」、今後のビジョンを“宣言”させていただく良い機会なのかなと思いました。その宣言も込めて、干支のトラ柄タタメルバイクCGアートをNFTプレゼントキャンペーンさせていただきました。
「ものづくりの思想」を応援していただく意味合いで、キャンペーンに応募いただける方が少しでもいたら嬉しいなと思います。
昨年コンセプトモデルが発表されて以降、海外でも大きな反響を呼んだ「ポータブル電源付き変形電動バイク」。机の下にも収納できるサイズの箱型からバイクに変形するため、駐車場が不要。家の中に置いてあってもおかしくないデザイン性と、ポータブル電源としての機能性を合わせ持つ。国内最大級オリジナルハードウェアコンテスト「GUGEN 2021」大賞など。
ーー「ものづくりの思想」について詳しくお聞かせいただけますか?
生駒)私はプロダクトデザイナーとして玩具やロボットなど様々な商品デザインを担当してきた経験をもとに、ICOMAで「ものづくりとコンテンツの融合」を実現したいと考えています。
例えば、いまファッション界のメーカーはものすごい勢いでメタバース、NFTに参入していますよね。あれはファッションが自分のライフスタイルを表現する「コンテンツ」であり、服やスニーカーはアートと融合しやすいシンプルなプロダクトデザインになっているからです。
一方でバイクはどうでしょうか?
バイクは乗り物としての機能が目につくと思いますが、いろんなモビリティがある中で「現代であえてバイクを持つ」意味というのはライフスタイルの表現、つまり「コンテンツ」になりつつあるのだと考えています。
しかしながら、一般的なバイクは満たすべき機能実現を重視したプロダクトデザインになりがちで、ライフスタイル表現としてのカスタマイズ性は低い。
私はICOMA タタメルバイクを単なる乗り物としてではなく、様々な環境に適応し、ライフスタイルを表現するツールの一つとして提案したいと考えてプロダクトデザインしています。

場所を選ばずに電源としてキャンプやワーケーションにも使っていただけるのもその1つですし、このコンセプトが一定の反応をいただけているのが現状なのかなと思います。
“アートバイク”としての可能性
ーータタメルバイクは今回のデジタルアートのほかにガレージキットなどでも、様々なデザインバリエーションの可能性を発表されていますね。
生駒)タタメルバイクは変形して楽しいだけでなく、シンプルな箱型だからこそデザインカスタマイズのバリエーションも無限大です。今後は例えばアーティストコラボバイクも作れるでしょう。
今回のNFTもその一例として、プロジェクトを応援してくださっているイギリスのデザイナーさんにアートを作っていただきました。

ただ、よく“痛車”とかに代表される一点もののデザインカーがありますが、欲しいと思うことはあっても、実際に買いますか?そして買ったとしても普段から乗って使いますか?
ーーかっこいいと思っても、実際に買ったり使ったりするのはなかなかハードルが高いですよね。
生駒)そうなんです。その所有欲を満たすのがおもちゃの役割だったりするわけですが、近年のNFTも含めた技術革新で、プロダクトデザインのあり方に大きな地殻変動が起きてると感じているんです。
私が着目している変化は大きく3つで、
1つめは、私が「ものづくりの民主化」と呼んでいる、3Dプリンターなどを活用した非中央集権的なものづくりの登場。
2つめは、NFTによる「所有欲の満たし方の変化」。
3つめはバーチャル空間のような「物理法則がない世界」に人が滞在するようになっていること。バーチャル空間におけるプロダクトデザインはリアル世界とは異なるはずです。
ICOMAのタタメルバイクはシンプルな構造設計ゆえに、3Dプリンターなどを活用し、小ロットで様々な場所で製造することが可能です。“ご当地バイク”みたいな形で、アーティストやメーカーと様々なコラボレーションがありうるでしょう。
そしてそこで「欲しい!」と思っていただいたときに、これまでは実車を買うしかなかったものが、「NFTを持つ」というあたらしい所有欲の満たし方も生まれてきました。
さらにはバーチャル空間で実際に使っていただき、「コンテンツ」として消費していただきやすいシンプルなデザインにもなっています。
まさに私がやりたかった「ものづくりとコンテンツの融合」を実現するハードルが、様々な技術革新によって一気に切り開かれている感覚があるんです。だからといって、まだこれといった明確な方法までは見えていないのですが、、、。

バーチャルとリアリティを「バイク」で行き来させたい
ーー「ものづくりとコンテンツの融合」、面白そうです!たしかに今はみなさんが暗中模索の状態が続いていますが。
生駒)はい。とにかく、やってみないとわからないですよね。
ここで私なりの仮説が一つあります。
ワープもできる、どんな物理的法則を無視できるバーチャル空間に人が移っても、「あえてバイクに乗ってダラダラ移動したい人」って絶対にいるんじゃないかって(笑)。だとすると、バーチャル空間で流行ったバイクが現実世界でも欲しくなる、という流れだってありうるはずです。
私が携わった「おもちゃ」というプロダクトはまさにそうで、アニメや映画などのコンテンツから憧れが生まれ、モノが欲しくなって売れます。そして逆に、リアリティなモノがあるからこそ、コンテンツに説得力が増し、さらにそのコンテンツが好きになる。
まさに「ものづくりとコンテンツの融合」の成功事例がおもちゃなのです。
私はリアル世界でハードウェアプロダクトを企画開発できる自分達の強みをいかしながら、コンテンツとしてのバイクを発信していきたい。
バーチャル世界で流行ったタタメルバイクを、現実世界でも乗る。そんなバーチャルとリアリティを行き来できる未来になったらワクワクしますよね!
ーーありがとうございます。最後にHINATAへの期待などがあればお聞かせください。
生駒)いま世界中のあらゆるプレーヤーやアーティストがNFT業界に参入していて、プラットフォーマーも含めてすでに一巡している感はあるのかなと思っています。単なるデジタルアートではよほどのクオリティやブランド力、資金力、特殊性がないと差別化できません。
なので次のフェーズに向けた、日本らしい仕掛けがあればいいのかなと思っています。
HINATAさんの「スポンサー機能」はその1つかなと思っていて、今回は試験的にプロモーション戦略やクリエイティブ制作、ガレージキット販売などで創業期からご一緒いただいているOKBさんにライセンシーとしてスポンサードしていただきました。
今後地方自治体やメーカーなどとコラボバイクを作った際にも、その機能を活用してコンテンツ発信として面白い取り組みができるかもしれません。
日本の強みでもあるリアル世界のものづくりと、デジタルコンテンツを融合させて世界に広めていく。そんな新しい仕掛けが日本から生むことができればと嬉しいなと思います。

ICOMA Inc.
NFTプラットフォーム「HINATA」(2022年1月11日公開)