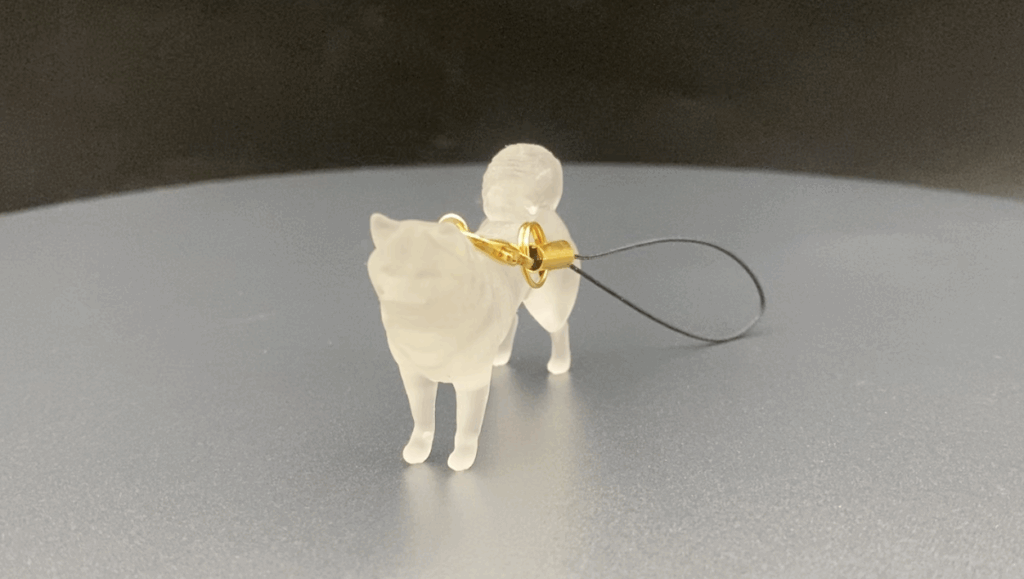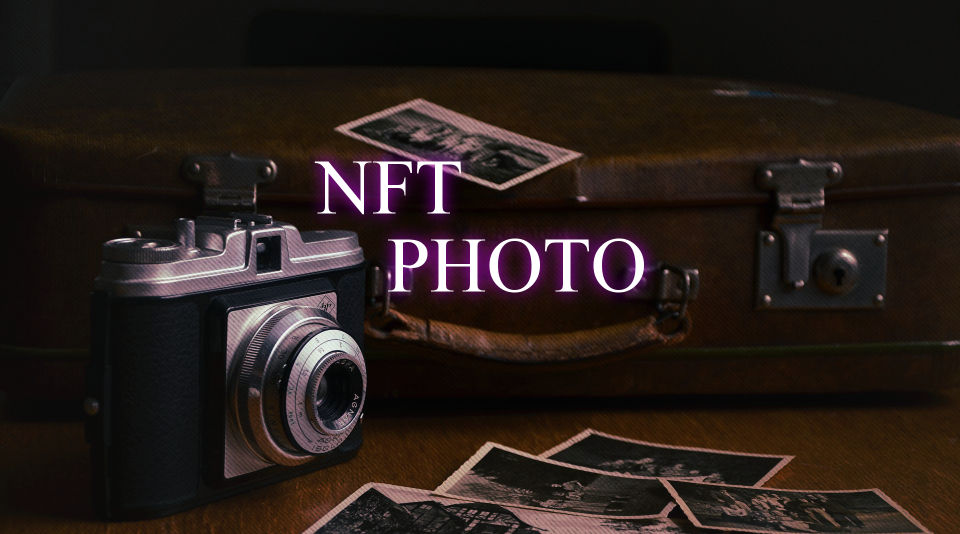Magazine
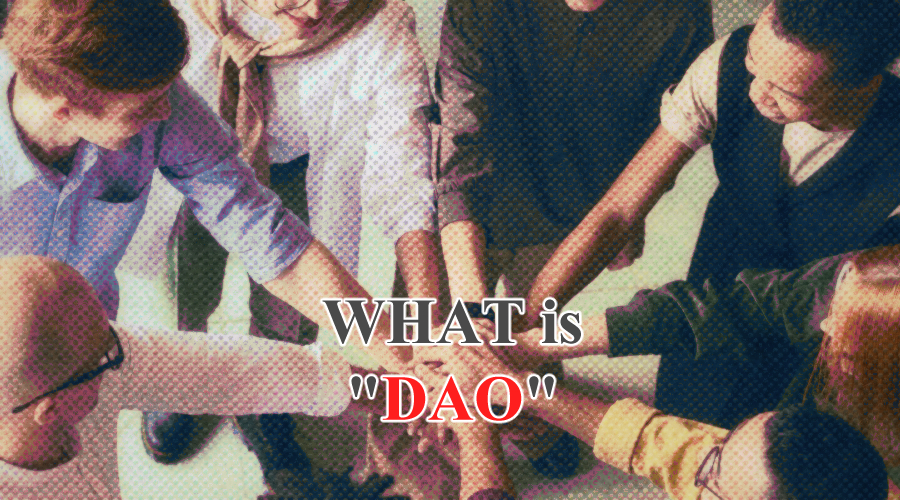
いま注目のDAO(分散型自律組織)とは?初心者向けに簡単解説!
- Information
最近では、暗号資産やNFT、メタバースといった言葉に関連して「DAO(ダオ)」という言葉を目にする機会も増えています。
そうした中で、DAO=分散型自律組織という解説を見ても、「いまいち理解できない」「結局なにがスゴいのかわからない……」と思う方もいるはずです。
この記事ではDAOについて、既存の組織と比べながら分かりやすく解説していきます。
世界中が注目している「DAO」の理解を深めていきましょう。
1.DAOとは
DAOとは「Decentralized Autonomous Organization」の略で、直訳すると「分散型自律組織」という意味です。
| 用語 | 日本語訳 | 読み方※ |
|---|---|---|
| Decentralized | 分散型 | ディセントラライズド |
| Autonomous | 自律 | オートノマス |
| Organization | 組織 | オーガニゼーション |
「分散化されて自律している組織」というのを理解するために、3つの特徴を解説していきます。
- 組織の意思決定はユーザー主体で行われる
- プログラムありきで組織が運営されている
- 運営の透明性が高いことで信頼されている
一見すると難しそうですが、既存の組織と比較するとイメージしやすくなるので、株式会社と比べながら見ていきましょう。
(1)DAOの特徴①:組織の意思決定はユーザー主体で行われる
DAOの場合、組織の方向性や活動内容を決めるときは、参加ユーザーによる投票が行われます。多くの場合、投票にはガバナンストークンが用いられます。
ガバナンストークンとは、保有している量によって投票の重みが変わるもので、株式会社でいう「株式」のようなイメージです。ガバナンストークンは暗号資産として、取引所で売買されているものもあるため、株式のように購入して保有量を上げることもできます。
しかし、株式との大きな違いは「DAO内での活動によっても付与される」という点です。
DAOの参加ユーザーは、DAOへ貢献することでガバナンストークンを報酬としてもらえる仕組みもあります。もちろん、その報酬の有無や量なども、ユーザーによる投票で決められるので、資金量の多さや影響力の大きさだけに左右されるわけではありません。
参加ユーザーは、ガバナンストークンを多く保有するために精力的に活動し、DAOの発展に貢献しようとします。DAOが発展すれば、より多くのユーザーが参加したり、ガバナンストークン自体の価値が上がったりするため、参加ユーザーへのインセンティブが働くようになります。
この参加ユーザーへのインセンティブや、ガバナンストークンという仕組みによって、DAOは自律的に運営されているというわけです。
(2)DAOの特徴②:プログラムありきで組織が運営されている
DAOはブロックチェーンやスマートコントラクトといった、プログラムありきで運営されています。
ブロックチェーンとは、ユーザー同士で記録の正しさを証明し、改ざんや不正をされにくくする技術です。スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上で動く、自動契約の履行を可能にするためのプログラムを指します。
DAOではユーザーの投票によって決まった内容は、スマートコントラクトで自動化され、改ざんや不正が起きないようにブロックチェーンに記録されます。このように契約や承認をプログラムによって自動化することで、ロスやミスを減らすというのもDAOの特徴です。
こういった最先端の技術を用いて運営されることから、DAOは「インターネットネイティブな組織」と言われることもあります。
たとえば、最近よく耳にするIoTやDXは、既存の物やサービス、仕組みにインターネットやAIを活用しようという動きです。一方で、DAOは初めからインターネット上で立ち上がる組織のため、インターネットおよびプログラムが運営のベースにあります。
既存の株式会社のように、意思決定をする株主総会や取締役が存在しないので、意思決定の早さや柔軟性に優れている点もDAOのメリットです。
(3)DAOの特徴③:運営の透明性が高いことで信頼されている
DAOは、基本的に誰でも参加できます。参加はもちろん離脱するときも、書面を取り交わす必要はありません。
DAOに誰が参加しているか、どのような活動が行われているかといったことは、誰でも確認できます。
DAOのコンテンツに関しても、ユーザーなら自由に利用可能です。また、DAOの運営に関わるプログラムも「オープンソース」といって、コードが公開されています。
このように誰でも参加できて、内部の事情をすべて公開していることで、透明性が高くなりDAO自体が信頼されるというわけです。
運営の中心組織を作らずに、ユーザー主体で意思決定するため、これまでの組織とは違った存在になると注目されています。
2.DAOの事例
DAOの事例を3つ紹介します。
- 通貨の常識を変えるDAO「Bitcoin(ビットコイン)」
- 新たな金融サービス「Maker DAO(メイカー・ダオ)」
- クリエイティブを促進「Ninja DAO(ニンジャ・ダオ)」
(1)通貨の常識を変えるDAO「Bitcoin(ビットコイン)」
画像:Bitcoin.org
暗号資産(仮想通貨)のキングである「Bitcoin(ビットコイン)」はDAOとして運営されています。DAOに関する議論の中では「現時点で正真正銘のDAOはビットコインしかない」という意見もあるほどです。
ビットコインは、2008年にサトシ・ナカモトが公開した論文をきっかけに誕生しました。論文には既存の金融サービスの問題点と、それを解決するためのビットコインのコンセプトが書かれています(参照:ビットコイン: P2P 電子通貨システム|Bitcoin.org)。
この論文に書かれているコンセプトや仕組みに共感したエンジニア達が集まり、コミュニティを作って開発を進めた結果、ビットコインが誕生しました。
この開発者コミュニティは、現在もビットコインの改善や運営を支えており、まさにDAOという形で運営されています。
(2)新たな金融サービス「Maker DAO(メイカー・ダオ)」
画像:Maker DAO
Maker DAOは、DeFi(ディファイ)を代表するプロジェクトです。DeFiとは、Decentralized Financeの頭文字で「分散型金融」を意味します。
これまでの金融サービスは、銀行や証券会社などの組織によって、取引を仲介するのが当たり前でした。一方、DeFiではスマートコントラクトを活用し、ユーザー同士が直接取引することが可能です。
これにより仲介手数料を安く抑えることができ、取引にかかる時間も短縮できるため、既存の金融サービスを変えるシステムとして注目されています。
DeFiには、さまざまなプロジェクトが存在しています。なかでもMaker DAOは、規模の大きさや信頼度の高さから、世界中で利用されているDeFiプロジェクトのひとつです。
プロジェクトのシステム変更や改善に関わることは、MKR(メイカー)というガバナンストークンを使い、DAO内での投票によって決められます。
DAOによる運営の透明性の高さや、プログラムによる取引の効率化など、新しい金融サービスとして注目されているのが、DeFiおよびMaker DAOです。
(3)クリエイティブを促進「Ninja DAO(ニンジャ・ダオ)」
画像:Ninja DAO
Ninja DAOとは、インフルエンサーのイケハヤ氏(イケダ ハヤト氏)が立ち上げた、国内最大級のDAOです。
Ninja DAOでは「Crypto Ninja(クリプト・ニンジャ)」というNFT作品を中心とした、さまざまなコンテンツが展開されています。
Crypto Ninjaは、これまでのアート作品では敬遠されていた「二次創作」を全面的に許可しています。規約の範囲であれば、Crypto Ninjaをモチーフにしたアートやグッズを販売しても良いということです(参照:イケハヤ氏のツイートより)。
これにより、多くのクリエイターが自分のスキルを活かして、二次創作の作品を生み出しています。Crypto Ninjaの公式サイトに「ここは、誰もが主役になれる里」とあるように、クリエイティブ活動を促進するDAOのひとつです。
また、Ninja DAOのメインコンテンツであるCrypto NinjaのNFT保有者を、DAO内での投票によって決めるという取り組みもされています。
多くのDAOが海外発で、やり取りも英語でされている中、日本人の参加者が多いのも特徴です。Ninja DAOは誰でも参加できるので、DAOがどういったものか体験してみたい方は、公式Discordから入ってみるのも良いでしょう。
3.DAOが注目されている理由
ここまでの解説からもわかるように、DAOが注目されている理由は「組織のあり方を変えるから」です。
DAOという言葉自体は、イーサリアム創設者のヴィタリック・ブテリン氏が考案したもので、2014年ごろから存在していました。
それが2020年ごろから、暗号資産をはじめNFTやDeFi、メタバースといった言葉がバズワードになり、運営元であるDAOも注目されるようになったのです。
これまでの組織は、運営者と参加者といったように、主従関係がはっきりしていました。関係がはっきりしていることでルールが明確になり、参加者が迷わず動けるなどのメリットはあります。
しかし、利益や権利がトップの組織に集中してしまうというデメリットもあるのです。
DAOでは参加ユーザーが主体となり、透明性の高い運営がされることから「これまでの組織のあり方を変えるのではないか」と注目されています。
4.DAOの課題と利用するときの注意点
DAOの課題と利用するときの注意点を「参加側」と「運営側」に分けて解説します。
参加側になることが多いかもしれませんが、運営側の注意点も知っておくことで、トラブルに巻き込まれるリスクを避けることができます。
くわしく見ていきましょう。
(1)参加側
参加側の注意点は「不正を働くユーザーも存在する」ということです。
DAOの発展に貢献しようとする人だけでなく、なかにはDAOに対して不正を働くユーザーも存在します。あるいは、DAOの参加ユーザーに対して、ハッキングや詐欺を行うユーザーもいるため注意が必要です。
実際に、DAOに参加すると見知らぬユーザーから、URL付きのDM(ダイレクトメッセージ)が送られてくることがあります。URLを開くと、詐欺サイトへ誘導されたり、デバイスがウイルス感染したりするため要注意です。
ほかには、DAOの公式アカウントを装ってメッセージを送ってくる事例もあります。
対策としては、これまでのインターネットトラブルと同様に、自分の身を守るための行動を取りましょう。
- 怪しいURLは開かない
- 相手の身元を確認する
- 個人情報は絶対に公開しない
- 身に覚えのないメッセージに返信しない
- 資金を投じる場合はかならず余剰資金で行う
インターネットネイティブな組織であるDAOは、多くの利点がある反面「相手の顔が見えない、身元が分からない」といった注意点もあります。
上記の対策を念頭において、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。
(2)運営側
運営側の注意点としては「お金関係がかなりグレーゾーンである」ということです。
DAOは世界中からユーザーが参加し、ガバナンストークンには暗号資産を使います。
DAOはどこかの国や地域に事務所を構えたり、法人登記をしたりするわけではないので、税金などの「お金」に関してはかなりグレーゾーンです。
世界的に見ても「暗号資産・DAO・NFT・DeFi・メタバース」といったWeb3.0といわれるジャンルは、法整備が進んでいません。
日本でもようやく、Web3.0に関する法整備を進める動きが出てきましたが、Web3.0の発展スピードに対して遅れをとっているのが現状です。
5.DAOに関連する主な銘柄
DAOに関連する銘柄は、以下のようなものがあります。
- BTC(Bitcoin)
- ETH(Ethreum)
- MKR(MakerDAO)
- BIT(BitDAO)
- UNI(Uniswap)
- COMP(Compound)
これらはガバナンストークンとして用いられるもので、保有していればDAOの意思決定に関わることが可能です。
また、ガバナンストークンとしてだけでなく、ひとつの金融商品として投資されているものもあります。
ちなみにBITやUNIなどは、海外取引所を使わないと購入できません。海外取引所を使う場合も、国内の取引所から元手となる暗号資産を送るので、まだ国内の取引所を開設していない方は作っておきましょう。
6.新しい組織「DAO」はこれからに要注目
最後に本記事の内容をまとめます。
- DAOは「分散型自律組織」と呼ばれる新しい組織の形
- 既存の株式会社にはないメリットがあり世界中が注目している
- DAOは基本的に誰でも参加可能で組織の意思決定に関わることができる
DAOの対比として、株式会社を例にあげて解説してきました。株式会社という組織の形は、100年以上前に作られたものです。
一方で、DAOは2014年ごろに生まれた言葉であり、概念です。これから、さまざまなDAOが生まれ、問題や課題を解決しながら発展していくでしょう。
DAOに興味がある方は、記事内で紹介したものをはじめ、気になるDAOに参加してみてはいかがでしょうか。

2020年にビットコインを購入したのがきっかけで、ブロックチェーンやNFTに興味を持ちました。
普段は暗号資産やNFT専門の、フリーランスWebライターとして活動しています!
より多くの人にWeb3.0の魅力を伝えるべく「難しそうなことも分かりやすく」をモットーに執筆します。
個人としても、NFTやメタバースに関するブログを運営中です!
世界を変える「Web3.0」は、日本を救う分野だと信じています!